危険なおもちゃ、流通規制を強化へ
子育てノウハウ
2024.10.11
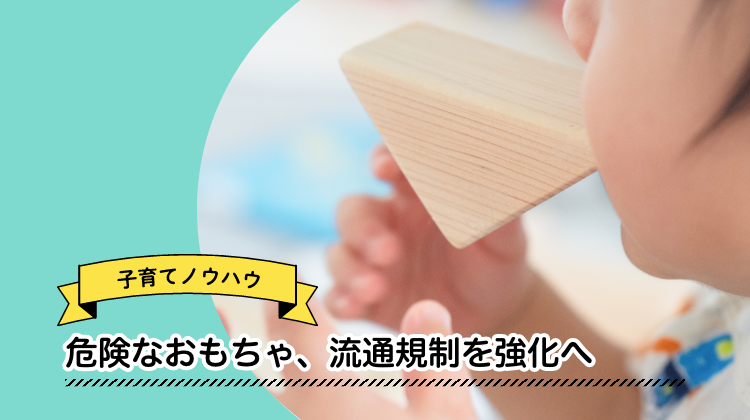
6月に、子どもの安全を脅かす可能性のある粗悪なおもちゃの流通を防止するための改正法が成立しました。この改正法により、おもちゃや子ども向け製品の製造および輸入に対して国が新たな安全基準を設定することが義務付けられました。また、海外の事業者も販売規制の対象となり、子どもたちの安全をより確実なものとします。
(※2024年7月3日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
改正消費生活用製品安全法で子どもの安全を確保する取り組み
近年、小さな磁力の強い部品を使ったおもちゃで、子どもが誤って飲み込んでしまい、開腹手術が必要になる事故が相次いで発生しています。これらのおもちゃは主に海外製で、インターネットを通じて販売されていました。中には、3歳の男の子が直径35ミリのボールを吸い込んで窒息し、亡くなるという悲惨な事故も発生しています。
こうした事故から子どもを守るために改正されたのが、消費生活用製品安全法です。この法律では、現在ライターやレーザーポインターなど12品目が消費者に危害を及ぼす恐れがある製品として指定されています。これらの製品は、国が定めた安全基準を満たさなければ販売することができません。今回、この指定品目に新たにおもちゃや子ども向け製品が加えられ、海外事業者も規制の対象となることが明確にされました。
さらに、海外の事業者が輸入業者を通さずに日本の消費者へ直接販売する場合、国内で行政と対応できる「国内管理人」を選任することが義務化されました。
改正法による低年齢層向け製品の安全基準強化と通販時代の課題
低年齢層向けのおもちゃやベビーカー、抱っこひも、ベッドガードなどが、指定品目に追加される候補として挙がっています。これらの製品は、専門家による消費経済審議会での議論を経た後、経済産業省が政令で正式に定めることになります。その後、具体的な安全基準が策定され、安全基準を満たさない商品に対しては、指導や改善命令などの行政処分が可能となる仕組みです。
この法改正の背景には、通販サイトの普及が関係しています。日本国内で簡単に商品が購入できる一方で、販売元が海外で連絡先が分からないケースが多々見受けられます。
これまで日本には、おもちゃの安全を法的に確保する制度がなく、玩具業界の自主規制に依存していました。業界団体である「日本玩具協会」が国際基準に沿った安全基準を設け、メーカーが検査を受けた後、玩具安全マーク(STマーク)を付けて販売する形が一般的でした。店舗でのSTマークの普及率は約6~7割に達しています。
ネット販売の安全性確保に向けた法規制と技術的監視の必要性
日本玩具協会の津田博特別参与は、「誰が販売しているのかが分かりにくいネット通販には予期しない危険が潜んでいるため、法規制による対応が求められる」と述べています。また、日本技術士会登録の「子どもの安全研究グループ」に所属する森山哲さんは、「人の手による監視には限界があるため、AIなどの技術を活用し、ネット上を含む効率的な監視方法が必要だ」と指摘しています。
欧州におけるネット販売の安全基準と監視の課題
欧州では日本に先駆けておもちゃに関する法的な安全基準が設けられていますが、ネット販売は依然として大きな課題となっています。業界団体「欧州玩具協会」の2020年のリポートによれば、大手通販サイトで販売されていた無名ブランドのおもちゃ134品を調査したところ、実に76%がEUの安全基準に適合していない危険なものでした。
発見された危険の約8割は、小さな部品が外れ誤飲の恐れがあるものや、パッケージが薄く、顔に張り付いて呼吸困難を引き起こす可能性があるなどの物理的な危険でした。また、基準を超える化学物質が使用されていたケースも1割に及んでいます。
EUでは、安全基準を満たしたことを示す「CEマーク」がついたおもちゃのみが販売可能ですが、欧州委員会の担当者は「商品が多すぎてすべてを監視するのは不可能だ」と述べ、ネット販売に対する危機感を強めています。
ベビーシッターは積極的に安全なおもちゃを推奨しよう
ベビーシッターとして各家庭に派遣された方は、危ないおもちゃはきちんと見極めて、保護者に伝える、ということも必要になってくるかもしれません。
乳幼児が楽しく安全に遊べるように配慮をしていきましょう。
