福音館書店の月刊誌「母の友」72年の歴史に幕
子育てノウハウ
2025.05.09
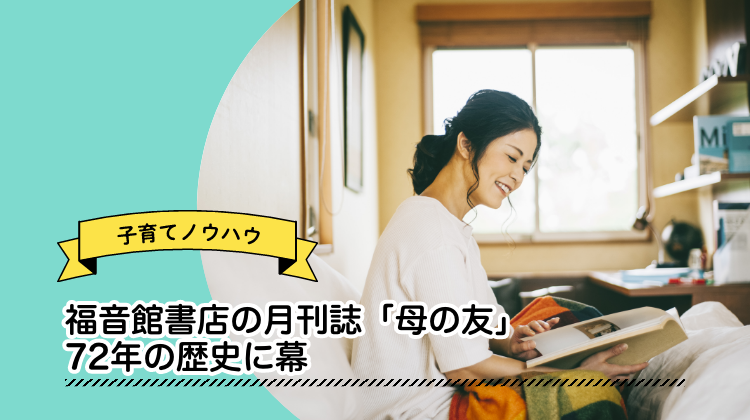
福音館書店が発行していた月刊誌「母の友」の最終号が、4月3日に店頭に並びました。
多くの子育てノウハウが掲載されていて、参考にしていた母親は多かったでしょう。
2015年より編集長を務めていた伊藤康さんは、翌4日夜に東京都世田谷区の書店で行われたトークイベントに登壇し、創刊から72年にわたる歴史を振り返りながら、読者や執筆者への感謝の気持ちを述べました。
ひとつの時代の終わりを感じさせる出来事ですね。
(※2025年2月19日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
言葉の持つ力に「焦点」共に歩んだ72年の軌跡
福音館書店が児童書の分野で培った経験をもとに、1953年に創刊した月刊誌「母の友」は、「幼い子と共に生きる人のための生活文化誌」として長年親しまれてきました。
本誌では、作家や画家による書き下ろしの童話やエッセー、さらには読者からの投稿などを通じて、「言葉」の持つ力に焦点を当ててきました。
最終号の特集テーマは「『生きる』を探しに」です。
編集長の伊藤康さんは、2022年に逝去された松居直さんが本誌を立ち上げた経緯について語っています。
松居さんは戦中戦後に兄3人を病気や戦争で亡くされた経験から、「生きることの意味を読者と共に考えたい」との思いで雑誌を創刊されたとのことです。
伊藤さんは、「休刊が決まってまもなく、この想いに立ち返り、最終号のテーマが自然と決まりました」と話されました。
戦後すぐに発行された経緯に、時代背景が感じられます。
多くの名作を育んだ雑誌、そして受け継がれる言葉
「母の友」は、多くの名作が生まれる場としても知られていました。
たとえば、昨年10月に89歳で亡くなられた中川李枝子さんによる童話「たまご」は、のちに「ぐりとぐら」へと発展する作品であり、初めて掲載されたのはこの雑誌でした。
また、角野栄子さんの代表作「魔女の宅急便」も、1980年代に「母の友」で連載されたのが初出です。
最終号では、中川さんが生前のインタビューや対談の中で語った言葉の一部が、抜粋されて再掲載されています。
「子どもを、ただ元気に育てたいと思ったとき、『よい子』に育てようなんて考えないでほしいの。(中略)本当のところ、子どもはみんな何かしら困った面を持っているのよ。でも、その“困ったところ”こそが、その子にとって大切な個性なの」
この言葉を朗読した伊藤さんは、感極まって声を詰まらせながら「中川さんの言葉には敵いません……」と静かに語りました。
さらに、「中川さんは『子どもが幸せでいるには、大人がまず幸せでないといけない』ともよくおっしゃっていました。
それは、この雑誌の根本的な思想だったのではないか」と振り返っています。
大人もハッとする子どもの言葉が教えてくれる世界のかたち
「母の友」のトークイベントには、投稿コーナー「こどものひろば」で2年間選者を務めた歌人・東直子さんも参加されました。
この欄では、子どもたちが日常の中でふと発した印象的な言葉が紹介されてきました。
東さんは、風に舞う花びらを見て「お花が走ってるよ」と語った子や、飛行機に乗って気圧の変化を感じた子が「僕の耳、行き止まりになったよ」と話したエピソードを披露しました。
東さんは、「子どもたちの言葉には、現実と空想の境がなく、すべてのものがいきいきと存在しているように見える。彼らのつぶやきに、私たち大人がはっとさせられる」と語りました。
会場からは、「まるで母校がなくなってしまうような寂しさを感じます」といった声もあがりました。
編集長の伊藤康さんは、「子どもと大人が対等に集える場でありたいと思って取り組んできましたが、それを守り続けることができなかったことに申し訳なさを感じています。そして、この雑誌を育ててくれた松居さんをはじめ、多くの先輩たちへの感謝の気持ちでいっぱいです」と胸の内を語りました。
なお、編集部のメンバー5人は今月末で解散となりますが、最終号が発行された今もなお、読者から感想や投稿のはがきが届き続けているそうです。
